貴族のように上品で、
マウントレーニアのカフェラテのようにやさしい、
日本産シスターフッド映画の代表作です。
作品情報
2015年に発表された山内マリコによる同名小説の映像化。生まれも育ちも異なる2人の女性が、東京で自分らしい生き方を模索する姿を描く。主人公2人を演じる門脇麦と水原希子をはじめ、実力派若手俳優が顔をそろえる。監督・脚本を務めるのは、本作が長編商業映画2作目となる岨手由貴子。
原作: 山内マリコ
出演: 門脇麦 / 水原希子 / 高良健吾 / 石橋静河 / 山下リオ ほか
監督: 岨手由貴子
脚本: 岨手由貴子
公開: 2021/02/26
上映時間: 124分
あらすじ
東京に生まれ、箱入り娘として何不自由なく成長し、「結婚=幸せ」と信じて疑わない華子。20代後半になり、結婚を考えていた恋人に振られ、初めて人生の岐路に立たされる。あらゆる手立てを使い、お相手探しに奔走した結果、ハンサムで良家の生まれである弁護士・幸一郎と出会う。幸一郎との結婚が決まり、順風満帆に思えたのだが…。一方、東京で働く美紀は富山生まれ。猛勉強の末に名門大学に入学し上京したが、学費が続かず、夜の世界で働くも中退。仕事にやりがいを感じているわけでもなく、都会にしがみつく意味を見いだせずにいた。幸一郎との大学の同期生であったことで、同じ東京で暮らしながら、別世界に生きる華子と出会うことになる。2人の人生が交錯した時、それぞれに思いもよらない世界が拓けていく―。
映画『あのこは貴族』公式サイトより引用
レビュー
このレビューは作品のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。
東京に潜む階層(セカイ)
本作の原作を書かれているのは、山内マリコさん。過去作『ここは退屈迎えに来て』では、自身の出身地である富山県を舞台に、地方で生活することの窮屈さを描いていました。『あのこは貴族』でも、東京と対になる「地方」として富山の風景が描写されています。彼女が感じている地方と都市部の様々な格差が、これらの作品に反映されていると言っていいでしょう。
小説から少し変わって映画版では、後日談を含めて6つの章で構成されています。一章「東京(とりわけその中心の、とある階層)」では、主人公の一人・榛原華子の過ごす日常が描かれます。
代々お金持ちである家系の箱入り娘として育てられた華子は、恋人と別れたことで今後の人生に不安を抱きます。周囲に結婚相手の候補を紹介してもらいますが、相性が良くない人ばかり。観ている私たちでも一瞬で分かる、絶望的な相性の悪さ。
なぜ観客でもすぐ察せられるのか。それは冒頭で既に、彼女の育ってきた環境がどのようなものかを的確に描いているからです。松濤にある実家の構造や交友関係、ジャムをつまみ食いする無作法な様子などから「本物の金持ち感」が見て取れました。
榛原家の会食の場で発せられる「映画やドラマでは出てこない文化もあるのよ。」という台詞。上流階級特有の慣習が、この世界の基準だと信じて疑っていないことが分かります。同時に彼らの環境が閉ざされたものであることが表現されています。
二章「外部(ある地方都市と女子の運命)」では、もう一人の主人公・時岡美紀のそれまでの人生が語られます。大学受験。故郷である富山からの上京。大学で実感する内部生と外部生の差。実家の家計の都合による中退。生計を立てるためのキャバクラでの仕事。華子とは打って変わり、辛いことも経験してきています。
前章で内側からの視点で描かれた東京を、上京してきた「外部生」からの別視点で見せる構成になっています。彼女たち自身の貧富の差というよりは、生まれた場所や育った環境の違いが原因のため、これからも埋まることのないことが痛々しく伝わってきました。
そんな対照的な二人の人生がはじめて交差するのが、三章「邂逅」。幸一郎と付き合っている華子と、大学からの友人である美紀。共通の知り合いである逸子によって引き合わされますが、喧嘩を起こすわけではなく、事実確認の会話をするだけでした。
ここが非常に新鮮に感じました。従来の映画やドラマであれば、異性の友人と交際相手が出会ったらすぐ喧嘩する先入観があります。しかしそういった女性同士の対立は本作では描かれず、代わりに連帯していこうという雰囲気が全編に流れています。
「普通」とは何か。二人の人生の対比構造には、この問いが隠されているのではないでしょうか。普通という概念は、個人個人で異なるもの。だからこそ自分の「普通」を押し付けるのではなく、事実として相手の「普通」を受け入れることが大切。三章まで観て、そう語りかけられているように思いました。
映像に落とし込まれた環境の違いと変化
前述した二つの階層を表現するために、この映画版では様々な映像的手法が用いられています。
まずは音の大きさ。華子側の物語を描くときは、上流階層の厳かさを表しているかのように静か。冒頭の会食をはじめとして、登場人物たちはほとんど物音を立てません。まるで観客も同じ場にいるような静かさを感じました。
対照的なのが、美紀が帰省した実家が映し出される二章の一場面。流れるテレビの音。個包装の食べ物の袋を開ける音。ガタガタという足音。といった音が混ざりあっています。一章のあとに耳にすることで「なんかうるさいな」という印象が強調されます。
音だけではなく視覚的にも、映像的な対比が多用されています。同じ大学生であっても、東京育ちの内部生と上京したての外部生が着ている服の雰囲気が、微妙に違っていたりします。
服以外の美術としては、美紀は大学時代にボロボロのガラケーを使っていました。対して、華子や逸子はスマホとタブレットを併用しています。こういった描写の積み重ねが、作品世界の実在感を強固なものにしています。
階層そのものを表現するシンボル的な存在も、映画の中に登場していました。たとえば美紀が参加したパーティーに置かれていたマカロンタワー。美紀と逸子が、マカロンタワーのどの位置にあるマカロンを食べるかで、二人の階層を暗喩しています。
同じように東京タワーも、象徴的に登場します。現在に至るまで東京のシンボルとして知られる建造物。そんな東京タワーが色々な角度から映し出されます。タワーを見ている人物が、どの場所にいるのか、すなわちどの階層にいるのか、を暗示しているのでしょう。
このように東京に潜む階層を丁寧に描写していく中、四章「結婚」と五章「彷徨」で物語は大きく展開します。それまで主人公二人がなんとなく感じていた息苦しさが顕在化します。
それまで華子が正しいと信じていた価値観が狂い始めます。自分の家よりさらにお金持ちの、政治家一族である青木家の幸一郎と結婚していました。しかし徐々に、妻として家の中に収まる役割に疑問を抱き、仕事をしたいと思うようになります。そのようななことが名家で許されるわけがなく、最終的に二人は別れます。
彼女はその後、美紀と偶然に再会します。美紀の家で交わされる二人の間には、階層の壁なんてものはありませんでした。この会話シーンは、間違いなく今作の白眉となる愛おしい場面。今まで違う角度から眺めていた東京タワーを、そこで同じ角度で眺める。そのカットに心を奪われました。
東京タワーと同様に、象徴的なアイテムとして用いられているのが乗り物です。美紀は富山でも東京でも、自転車を使って移動しています。富山に帰省した際は、散乱したゴミ袋が邪魔して道をまっすぐ進めないことがありました。この場面は、美紀が歩んできた人生そのものを表しているように思えました。
対して華子は、常にタクシーに乗って移動していました。タクシーは運転手がおいて、自分はただ乗っているだけ。まるで親族によって夢や人生を与えられてきた、華子の受動的な人生を表現しているかのようです。
そんな中クライマックスで、彼女は自分の意思でタクシーを降ります。そして美紀の家からの帰り道、自分の足で歩く華子の姿がそこにはありました。はじめて自身の人生を選択したことを映像的に見せています。最後に描かれる一年後では、自分で車を運転しています。一連のシークエンスを切り取ってみみても、本作が映像的に非常に作り込まれているかが分かります。
旧来的な価値観の世界から脱却した華子。一年後の発表会の場面では、その立ち位置が視覚的に表現されていました。『パラサイト 半地下の家族』(2019)に代表される階段を使った構図です。ステージと同じ階で鑑賞する一般市民。上の階から眺める幸一郎。そして階段の途中で立っている華子。どちらにも属していない彼女の現在を示しています。
あまり気持ちを表に出さない彼女が、にこっと微笑むラスト。このカットは冒頭の写真撮影と呼応しています。そのときは見せなかった笑みは、自身の決断を誇りに思っているようでした。
上品でやさしいシスターフッド
主要キャラクターを演じる方々はみな演技力が高く、そのおかげで登場人物一人ひとりが魅力的に映っています。特筆すべきは、なんといっても幸一郎。演じている高良健吾さんが、上流階級の強者感を醸し出していました。
彼の登場前に「残念」な男たちを複数見せることで、完璧さが引き立てられています。華子が最初に会ったときに、ボーッとしてしまうのも頷ける強者オーラ。頭のてっぺんから足先まで、幸一郎というパーフェクト人間を体現していました。
ちなみにこの際のレストランでの注文を巡るやり取りは、劇場で複数から笑いが起きており、全編通して一番の爆笑シーンだと思います。
華子を演じる門脇麦さんは、自分から多くを語らない難しい役どころを見事に好演されていました。美紀を演じる水原希子さんは、クールなイメージとは程遠い、地方出身の大学生にしっかり見えたので役作りの凄さに感動しました。
この映画は「都会を舞台に織りなすシスターフッドムービーの新境地」という紹介がされています。シスターフッドとは、
ウーマン・リブの運動の中でよく使われた言葉で,女性解放という大きな目標に従った女性同士の連帯のこと。
シスターフッドとは – コトバンクより引用
を指し、MeToo運動以降、再注目されるようになりました。
時代を同じくして、女性が連帯して活躍する映画の数は激増しています。一例を挙げると、『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』(2019)や『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019)、『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』(2020)など、ジャンルも多岐にわたっています。
ここまで述べたように今作でも、女性たちが協力して問題に立ち向かう様子が描かれています。
華子は結婚後しばらくして、仕事を始めたいと思うようになります。しかし名家に嫁いだ身でありながら、許されるわけがありません。この頃の彼女が夫を見送る様子を映したカットがとても印象的。家の外から引き気味で華子を撮っており、外に出られず「家」に囚われている状況が表現されています。
美紀も同様に、男性=幸一郎に依存した自分の仕事を変えようと思っていました。二人は異なる階層にいながら、似たような悩みを抱いていました。
劇中に登場する「女性を分断する考えがまかり通っている」という台詞。独身女性と既婚女性であったり、ママ友同士であったり、女性は対立構造に置かれる傾向がよく見られます。実際はそうではなく、美紀から華子への「私たち似ているね」という一言が示すように、協力し合う存在なのです。
男性優位な社会に囚われていた主人公二人。彼らだけでなく幸一郎もまた、前時代的な価値観に囚われています。夢を持ったところで血筋の宿命には決して抗えない。だからこそ家父長的な男性性を保ち続けることを受け入れるしかありませんでした。
高良さんの表情には、現実に対する諦めゆえのドライさや切なさがあるように感じました。幸一郎を一方的な加害者ではなく、男性性に囚われた被害者としても描いており、フェアな作品という印象を受けました。
ガールズエンパワーメント的な価値観が台頭する一方で、一部では旧来的な家父長制も根強く残っている現代の東京。今作はそんな東京ならではのシスターフッドムービーと言えます。
「東京は住み分けがされている。」「東京は違う階層の人とは出会わないようにできている。」劇中でも言及されているように分断が起きている東京の特殊性が、シスターフッドとしてのメッセージをよりに明確にしています。
物語終盤、華子は自転車に2ケツするギャルたちを見かけます。普段は分け隔てられている別の階層の人物との邂逅。名前も知らないし、その後の人生で二度と会わないかもしれない。しかし確かに心を通わせることができた。この場面には、今作独特の語り口のやさしさが表れているように思いました。
自分らしく生きることの大切さを伝えるメッセージ。押しつけがましく突きつけてくると言うよりは、「こんな生き方もいいよね」と語りかけてくるようでした。旧来的な価値観からのアップデートをしつつ、鑑賞後は観た人それぞれに寄り添ってくれるような上品な映画です。
最後に
映像的に作り込まれているので、何度観ても新しい発見ができる作品だと思います。そしてまだ観たことが無ければ、ぜひ観ていただきたいおススメの邦画です。
こんな時代もあったよね、と言えるように定期的に見返していきたいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
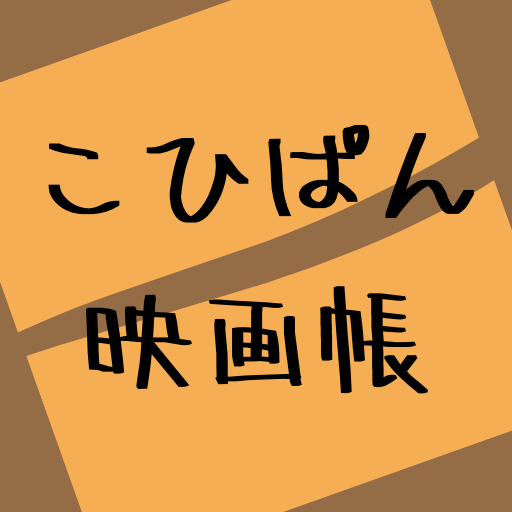


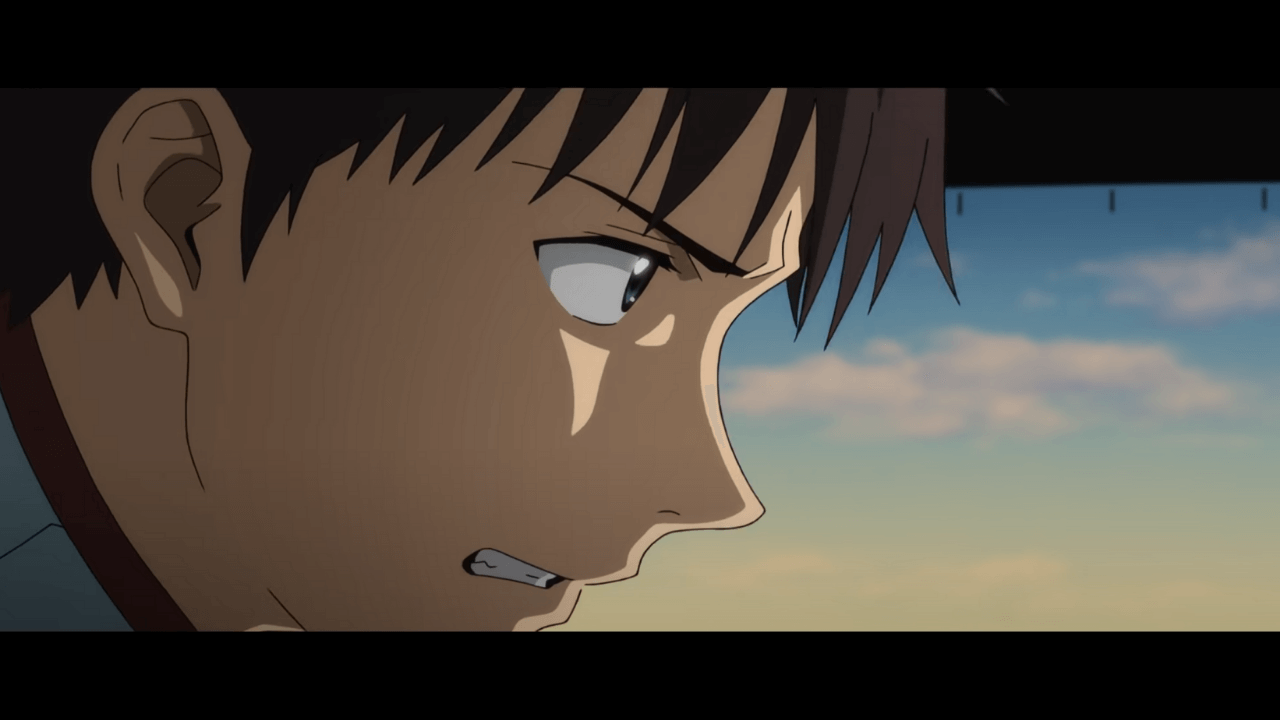
Comments