『時をかける少女』映像化の第8弾です。
他の『時をかける少女』関連記事はこちら。
作品情報
1965年に発表された筒井康隆による同名小説を、主演・仲里依紗で実写映画化。原作の主人公である芳山和子の娘・あかりが、1974年と2010年を行き来する後日譚的な作品。細田守監督による2006年のアニメ版に出演した仲里依紗が、再び主役を演じる。
原作: 筒井康隆『時をかける少女』
出演: 仲里依紗 / 中尾明慶 / 安田成美 ほか
監督: 谷口正晃
脚本: 菅野友恵
公開: 2010/03/13
上映時間: 122分
あらすじ
高校卒業を目前に控えた芳山あかりは、母・和子が薬学者として勤める大学にも無事合格し、新たな生活に胸を弾ませていた。
映画「時をかける少女」Blu-ray&DVD 10月13日発売決定!より引用
ところが、和子が交通事故に遭い事態は一転。
「過去に戻って、深町一夫に会わなくては・・・」と必死に訴えながら昏睡状態に陥った母の願いを叶えるため、
和子が開発した薬を使って1972年4月にタイム・リープすることを決心する。時空を飛び越え到着した過去の世界は、なんと1974年2月。間違えて行くべき場所から2年も経った時代に飛んでしまったあかりは、そこで偶然出会った映画監督志望の大学生・涼太とともに深町一夫探しを始める。
四畳半一間のアパートに同居し涼太の映画製作を手伝ううちに、やがてあかりは涼太に恋心を抱き始めるが・・・。
レビュー
このレビューは仲里依紗版をはじめとした、歴代『時をかける少女』映像化作品のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。
アフター「細田版時かけ」
2006年に公開されたアニメーション映画『時をかける少女』。当初の上映規模とは裏腹に、口コミが話題を呼んだことで大ヒットを遂げました。国内外で多くの賞を受賞しており、現在にいたるまで根強い人気を誇っています。
従来とは異なる物語を打ち出した細田守監督による時かけは、それまでの時かけのイメージを大きく塗り替えました。元気な女子高生が、偶然手に入れたタイムリープ能力を通し、人間として一歩成長する。このような明るいイメージが、一般に定着していると思われます。
それからわずか4年後の実写映画化。スパンの短さからして、アニメの人気を受けて企画されたのは明らかです。それが最も如実に表れているのが、主人公の配役。細田版でヒロインを演じた仲里依紗さんが、この作品でも主演を務めています。同作で彼女が放っていた輝きが、実写化製作の原動力となったのは否めません。
さらに今作の冒頭には、細田版を連想させるカットが差し込まれています。いきものがかりがカバーした『時をかける少女』が流れる中で画面に映し出されるのは、道を全速力で駆け抜ける仲さん。明らかにアニメの名シーンを意識した構図でした。
対照的にストーリーは原作寄りであり、芳山和子や深町一夫、浅倉吾朗が登場します。劇中において和子が深町と出会う時代は1972年であり、NHKドラマ『タイム・トラベラー』(1972)の設定と一致。また大林宣彦版と同様に、二人は恋愛感情を抱いています。主人公が弓道部に所属している点も、大林版に由来すると考えられます。
NHKドラマ版、大林版、そして細田版といったように、歴代の映像化の要素を美味しいところ取りした作品と言えます。
高校3年生の春、芳山あかりが大学の合格者発表を見に行くところから物語は始まる。娘から合格の報告を受けた母・和子。大学の研究者である彼女は、自主的にタイムリープの薬の開発に成功していた。
学生時代の自分と、謎の青年が一緒に映った写真を、一輪のラベンダーとともに渡された和子。ラベンダーを嗅ぐと、当時の光景が蘇ってきた。大学からの帰り道、その記憶に想いを巡らせていた彼女は、車と衝突してしまう。
入院中の和子は、開発した薬を使って深町一夫に会いに行ってほしいと、あかりに伝える。このとき和子は、タイムリープ先で何をするのか具体的に伝えていません。そのため時間移動のリスクを負わせてまで、娘にやらせるべきことなのか、という疑問が浮かんできます。
話の前提として、いかにして一介の研究者がタイムリープの薬を作れたのか。はたまた蟻がその場から消えただけで、なぜ時間移動の実証を確信できたのか。映画内のリアリティラインがはっきりしていないため、こうした展開の飲み込みにくさを抱えながら話は進んでいきます。
タイムリープ要素の希薄さ
1972年4月の土曜日、中学校の理科実験室。和子が開発した薬を飲み、時と場所を念じると、タイムリープが始まる。時計や恐竜の骨といった様々な事象がCGで描かれ、それにより時間移動が表現されています。過去の映像化と比較しても、チープな印象を受ける演出でした。
あかりは間違えて1974年2月に飛んでしまう。メインの舞台となる1974年の街並みの再現度が素晴らしい。ヘアスタイルや服装などの小道具から、駄菓子屋やホーロー看板などの大道具まで。解像度の高い昭和の描写の数々からは、製作陣のこだわりが伺えます。個人的には『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズを想起させられました。
この作品で特筆すべき点は、仲さんの演技の素晴らしさです。明るく健気なあかりからは、「今どき」の女子高生っぽさが滲み出ていました。彼女が書く独特な丸みを帯びた文字は、「まさに」といった字体。過去に飛んでから、戸惑いながら行動する様子も可愛らしかったです。
路頭に迷ったあかりは、偶然出会った溝呂木涼太の家に泊まらせてもらう。対照的な性格の二人のやり取りが、本当に愛おしい。最初は距離を置いていた彼らでしたが、深町の謎を追うにつれバディ感が徐々に強まっていき、やがてカップルに見えてきます。
中尾明慶さん演じる涼太が、1970年代にいそうな青年っぽい雰囲気を見事に纏っていました。もちろん現代から来たあかりとは、会話が全然嚙み合いません。500円玉や携帯電話などの件は、カルチャーギャップコメディとして笑える場面でした。
過去を舞台に繰り広げられるドラマが面白い反面、「時をかける」要素が希薄な作品でもあります。というのも主人公がタイムリープするのは、2010年から1974年への一度だけ。なのでそもそも、和子は娘をどのように現代へ帰らせるつもりだったのか、が最後まで引っかかる部分ではありました。
一回きりのタイムリープでは、時かけとしては珍しく、数十年という長い年月を移動します。その先であかりは、若き日の母親と父親に会います。
薬学部を目指して勉強していた高校生の和子、そして彼女の知り合いだったカメラマンのゴテツ。青木宗孝さん演じる彼はカッコよく、本作で特に強い存在感を放っていました。
過去に飛んだ主人公と両親の予期せぬ出会いは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)と非常に似ています。劇中のタイムリープの回数を考えても、それまでの時かけよりも話の系統が近いと思いました。
時かけである必然性
『ゴジラ』(1954)や『2001年宇宙の旅』(1968)のポスターを家に貼るほどの、SF映画オタクである涼太。所属している映画研究会では、自主製作映画『光の惑星』を撮影していた。未来人であるあかりとの別れを惜しむ彼は、その姿をフィルムに記録しておく。
深町と会えたあかりは現代へ帰ろうとするも、その日の夜、涼太が交通事故に遭う未来を知ってしまう。歴史を変えようとした彼女は深町に記憶を消され、現代に戻される。今日の別れが永遠の別れだと知っていても、自らの力では何もできない。そのもどかしさが伝わってきました。
鞄に入っていた『光の惑星』のフィルムを発見するあかり。いざ鑑賞すると、訳も分からず涙が流れてくるのでした。
涼太が撮影したフィルムと、和子と深町の写真は、本来の歴史では存在してはいけない人物を映している点で共通しています。他の時かけ映像化と同様に、写真がキーアイテムであるとともに、本作で重要なモチーフとなっているのが、映画。言うなれば「映画に刻まれる記憶」がテーマとも捉えられます。
涼太という一人の名もなき映画監督の物語と考えると、切なさがこみ上げてきます。ハラハラのクライマックスから、あかりが現代へ帰るまでの展開には落涙させられます。
しかしながら、上述してきたようにご都合主義的なストーリーや、過度に湿っぽい演出が全体的に見受けられました。また序盤に張られた伏線がわざとらしく、本編で種明かしされる前に容易に推測できた人もいたでしょう。
それに加え、和子と深町が登場するものの、二人に関するエピソードの深堀りにはほとんど時間が割かれていませんでした。そのため時を越えた彼らの再会にも、感動できません。あくまでこの物語は、原作や大林版などを知っている前提で作られている話。それらのファンに対する目配せにしか感じられず、残念に思いました。
満開の桜の道を歩くラストにも象徴されるように、桜が印象的に用いられています。母親である和子の記憶に結びついた植物は、ラベンダー。対して娘の記憶に結びついているのは、桜。ラベンダーから桜に受け継がれているのが分かります。
時かけは既に、大林版などの過去作品から細田版へと、イメージの代替わりを果たしていました。ただ今作は、あかりと涼太のドラマであったり、映画や桜のモチーフであったり、そのどちらとも異なる時かけを描こうとしています。しかし同時に、どちらの要素も盛り込んでいるため、結果的にぼんやりした印象は否めませんでした。
最後に
レンタルや配信で鑑賞できるこの映画。時かけの歴史を感じられるので、ぜひとも観ていただきたいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
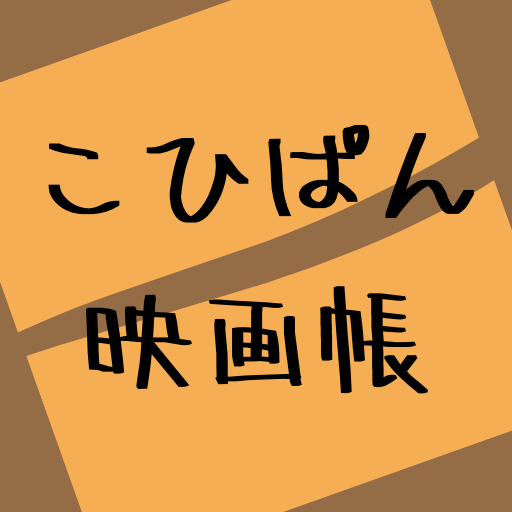



Comments