プール、インターハイ、そして甲子園。2020年を生きた高校生のあり得たかもしれない夏を描いた名戯曲。
作品情報
徳島市立高等学校演劇部による、第44回全国高等学校総合文化祭「2020こうち総文」/WEB SOUBUN出展作品。WEB SOUBUNでの上映に伴い、同戯曲の映画化が行われた。2019年に起きた女子生徒へのプール強要事件をモチーフに、高校生たちのある夏の一日を映し出す。
出演: 出島こころ / 吉成美玖 / 奥田千絃 / 水口結依 / 山賀祐奈
監督: 川原康臣
脚本: 中田夢花
配信: 2020/08/29 (YouTube)
上映時間: 65分
あらすじ
学校のプールは水深1.2メートル。だけど私が立っているここは水深ゼロメートル。セミの鳴き声はうるさいし、グラウンドで練習中の野球部は暑苦しいし、このプールには水なんか入ってないけど、私はここで泳いでみせる。グラウンドから飛んでくる砂に溺れたって、私は諦めない。水がなくても、泳ぐ方法はあるはず。そう信じて、私は腕を大きく回し、息継ぎをする。だって私はJKやもん。JKって無限の可能性秘めてると思わん? まぁ、わからんけど。
徳島市立高等学校演劇部Vol.23B『水深ゼロメートルから』/映画版 – YouTubeより引用
本編
こちらから視聴できます。
レビュー
このレビューは作品のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。
コロナ禍における挑戦
この映像作品の元となっているのは、徳島市立高等学校演劇部で上演された戯曲。2019年に同校の3年生だった中田夢花さんによって執筆された、オリジナルストーリーです。
同年に開催された第44回四国地区高等学校演劇研究大会では、最優秀賞である文部科学大臣賞と創作脚本賞を受賞しており、既に高い評価を得ていました。
翌年の第44回全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文)演劇部門にも出展されていた本作。全国高等学校総合文化祭は、高校演劇をはじめ、合唱や吹奏楽、美術や書道にいたるまで様々な文化活動の場であり、その活動をする高校生たちの目標とされてきました。
毎年7~8月に開催されており、2020年度は高知県で執り行われる予定でした。その予定を台無しにしたのが、新型コロナウイルスの世界的な流行。2020年2月あたりから日本でも感染が拡大していき、経済は大きな打撃を受けます。経済の停滞や行動の制限は、多くの文化活動に支障をもたらしました。
高校演劇業界も例外ではありません。高校で企画されていた卒業旅行や文化祭などの行事と同様にして、2020こうち総文も中止が発表されました。
演劇部の部員や関係者の方々が抱いた悲しみや葛藤は、当事者ではない立場からは容易に言葉にするはできません。ただ彼ら一人一人が、たくさん苦しみ、たくさん悩んだのは火を見るよりも明らかでしょう。
現地での開催に代わって、「WEB SOUBUN」の開催が決まりました。演劇部門(=全国高等学校演劇大会)は、ウェブ上で演劇を撮影した動画を上映する形式でした。
徳島市立高等学校は「上演の様子を撮影する」形ではなく、台本はそのままに「映画として撮影する」方法を選びます。出場した12校の中で唯一でした。顧問を務める村端先生は、「演劇を動画としてあげることに抵抗があったため、映像作品としてアップ」したのだそう(※1)。
※1:四国ブロック代表・徳島市立高等学校『水深ゼロメートルから』(作、中田夢花)|澤田大樹(TBSラジオ記者/国会担当/「高校演劇ZINE」監修)|noteより引用
未曾有の事態の最中での新たな試みに敬意を払うとともに、その努力の賜物をYouTubeで無料で観させていただくことに感謝です。
「性」という枠組みへの違和感
登場人物は5人。4人の女子生徒ココロ、ミク、チヅル、ユイに、教師の山本を加えた5人です。
水泳部の部長を務めるチヅルがたった一人で、水の張っていないプールでイメージトレーニングをしている場面から幕を開けます。今作の特徴なのが、このプールの上だけで最後まで物語が展開される点。舞台が他の場所に移動することはありません。
ここで連想するのが、昨年公開された『アルプススタンドのはしの方』(2020)。この映画も、2017年に全国高等学校演劇大会で最優秀賞を受賞した、兵庫県立東播磨高等学校演劇部による創作戯曲を原作としています。
甲子園を舞台にしながら、試合が行われているグラウンドを画面に映さずに、話を展開したこの作品。『水深ゼロメートルから』もそうですが、限定的な舞台設定は演劇的であると同時に、映画としては新鮮な印象を与えます。野球部が出てきたり、他にも共通点が挙げられる二作です。
さてストーリーに話を戻すと、プールにはチヅルのほかにも、友達のミクがいました。遅れてやってくるココロと二人で、水泳の補習に呼ばれていたのです。とはいえプールには水が張っていないので、掃除を言い渡されました。
序盤から中盤にかけては、高校生同士の他愛のない会話が繰り広げられます。感情の起伏はあまりなく、何気ない会話劇が続いていくだけなので、退屈に思う人もいるかもしれません。しかしながら、彼女たちの発する言葉の中には、ときどき違和感を抱かされました。
例えば、ミクの練習している阿波踊りについて。阿波踊りには、ダイナミックな動きの男踊りと、しなやかな動きの女踊りの、二種類の踊り方があると言います。ここからは伝統文化に表象されている性差、そしてその枠組みに対しての違和感のようなものが伝わってきました。
他にも地面に落ちているセミをブラシで掃く一連の流れなど、登場人物たちの台詞に含まれる問題提起のような表現を耳にするたびに、心がチクッとしました。
おそらくそれは、普通の友達同士ではあまり使わない言い回しでありながら、芯を食っている表現だからだと思います。また限定的な舞台設定が、この世界の閉塞感を強調しているのも大きいでしょう。
本作の下敷きになったのは、滋賀県の高校で2019年に起こった、生理中の女子生徒に対して水泳授業への参加を強要した事件。つい最近、しかも女子高生の身に起きた問題が一つの戯曲へと落とし込まれています。
プール上での会話の中で、なぜミクとココロが補習に呼ばれたのかが明らかになります。ミクは自身の身体のコンプレックスを理由に欠席。一方ココロは、生理でありながら参加を強要されたのをきっかけに、以降の授業を欠席。まさに上述の事件を、ビビッドに反映したようなキャラと言えます。
生理が何日目かを手続きしないと休めないという異常な制度。そこに畳みかけるように、堅物な教師が立ちはだかる。この時代錯誤な雰囲気も、ニュース記事とリンクしています。
女性として、一人の人間として
当時現役の高校生が脚本を書き上げただけあって、現代の高校生が抱いている感情や考えが如実に詰め込まれている今作。中盤までは「性」への違和感を少しずつ積み重ねていました。終盤になるに従って「女性らしく生きる」ことの是非を、浮き彫りにしていきます。
幼い頃はほとんど意識しなかった、外見や体力といった性別の違い。しかし成長するにつれ、その差は顕著になっていく。高校生は、子供と大人の境目にいる存在です。思春期の真っ只中にいる彼らが、どのように性差と向き合い、大人へなっていくかが描かれていくのです。
チヅルは野球部の生徒である楠に、水泳のタイムで負けたのをきっかけに、部活を辞めようとしていました。「女は男に勝てない」といった意見を受けながら、それでも男女「平等」な考え方のもと、あくまで彼と同じラインで戦おうとしています。
そんなチヅルと対照的な位置にいるのが、ココロです。既に男女の違いをまざまざと実感している彼女。性別による違いがあるのは前提なのだから、だったら女性らしく生きたほうが良いと考えています。当然メイクはするし、可愛くなるための自分磨きをする。生理と同様に、この二つも女性らしさを象徴しています。
男性中心の社会において、「女として」しか評価されない現実に対する諦観すら、彼女からは感じられます。諦めの境地として、女性らしい生き方を選択しているように映りました。
中盤までの会話劇で積み重ねられた「性」への違和感が、クライマックスの彼女の激昂によって一気に爆発。演者たちの素晴らしい演技も相まって、登場人物たちの剝き出しの感情の一つ一つが、私たちの心にグサッと刺さりました。女を捨てることと、女として生きること。それぞれの生きづらさが描かれています。
その息苦しさの要因の一つである、男性中心社会を象徴しているのが、野球部が練習しているグラウンドです。チヅルたちがいるプールは、グラウンドにいる野球部からは視界にすら入らない場所。劇中の台詞「マウンドからは私たちの姿は見えていないよ」は、社会に対する直接的なメッセージかのようです。
掃いても掃いても、風が吹けば新たに飛んでくるグラウンドの砂。ココロたちが砂の掃除に文句を言っている様子が、たびたび映し出されます。プールを綺麗にする掃除の無意味さは、「社会」から男性を完全に排除することの難しさに繋がっているようでした。
そういった生きづらい世の中であっても、自分の意思で選択し、自分らしくその道を生きる。その大切さが、各キャラが迎える顛末で表されていました。「JKなめんな」と叫び、ラストカットで微笑むココロは、自分らしく生きることの良さを確認したように見えます。その姿に感動しました。
本作はあくまで、演劇の映画化です。そのため派手な映画的演出やダイナミズムを期待すると、肩透かしをされるかもしれません。撮影場所やカメラアングルを変えているだけで基本的には実際の演劇と変わらず、本当に演劇を観ているときと同じ感覚を抱きました。ゆえに演劇の映画化という面では、大いに成功なのではないでしょうか。
架空の2020年を舞台にしながら、当時のリアルな剥き出しの高校生が映し出されています。そしてこの作品が、今を生きる高校生の手によって作られ、演じられたのが、とても意義深いものであるように思ってなりません。
最後に
2021年11月には、下北沢「劇」小劇場で商業舞台として上演され、ますます拡大を見せていく『水深ゼロメートルから』の世界。今後も目が離せません。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
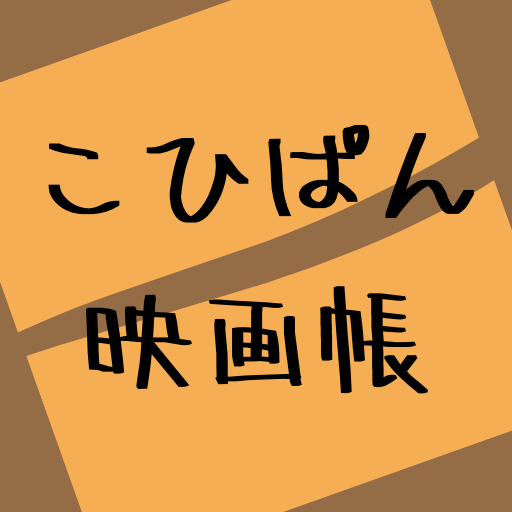
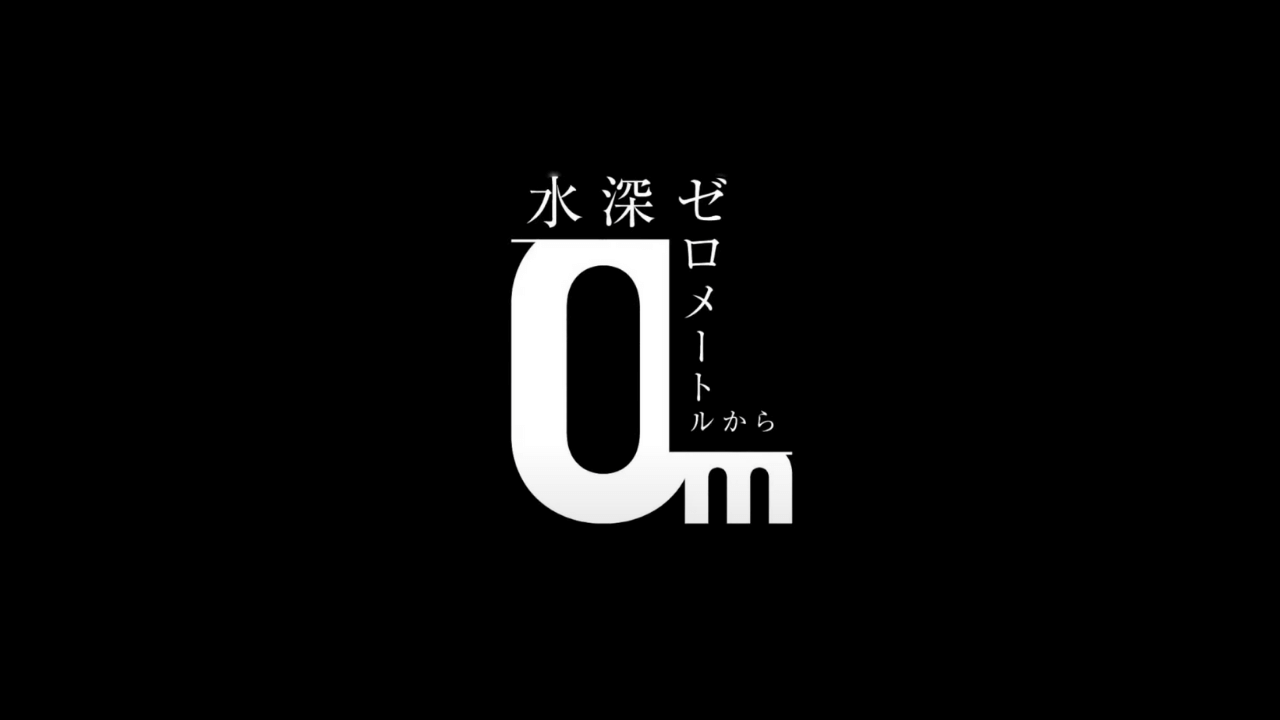


Comments