問題作にして、傑作。
作品情報
第34回柴田錬三郎賞を受賞した朝井リョウの同名小説を映画化。家庭環境、性的指向、容姿、様々に異なる背景を持つ5人の人生が、少しずつ交差していく。第36回東京国際映画祭では、最優秀監督賞・観客賞を受賞した。
原作: 朝井リョウ『正欲』
出演: 稲垣吾郎 / 新垣結衣 / 磯村勇斗 / 佐藤寛太 / 東野絢香 ほか
監督: 岸善幸
脚本: 港岳彦
公開: 2023/11/10
上映時間: 134分
あらすじ
横浜に暮らす検事の寺井啓喜は、息子が不登校になり、教育方針を巡って妻と度々衝突している。広島のショッピングモールで販売員として働く桐生夏月は、実家暮らしで代わり映えのしない日々を繰り返している。ある日、中学のときに転校していった佐々木佳道が地元に戻ってきたことを知る。ダンスサークルに所属し、準ミスターに選ばれるほどの容姿を持つ諸橋大也。学園祭でダイバーシティをテーマにしたイベントで、大也が所属するダンスサークルの出演を計画した神戸八重子はそんな大也を気にしていた。
映画『正欲』公式サイトより引用
レビュー
このレビューは映画『正欲』および関連作品のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。
窮屈な社会の圧倒的リアリティ
作家・朝井リョウさんがデビュー10周年を記念して書き下ろした長編小説『正欲』。同じく10周年を記念して『朝日新聞』で連載された『スター』が「白版」と呼ばれているのに対して、「黒版」と称されています。発行部数は50万部を超え、第34回柴田錬三郎賞に輝きました(※1)。
※1:映画『正欲』公式サイトより引用
5人の人物の独白によって物語が語られ、それらが交差していく群像劇。その構成を踏襲するかのように今回の映画化では、人物の名前が画面に映し出された後、その人の話が展開されていきます。ただし基本的には、桐生夏月と佐々木佳道の物語を中心に据えているのが映画版の特徴です。
広島のショッピングモールにある寝具店で販売員をしている夏月は、実家暮らしの独身女性。家にいればアップデートとは無縁な両親からの圧力を感じ、職場にいれば楽しそうに生きるカップルや家族連れが嫌でも目に入ってくる。
そういった彼女が感じている生きにくさが、自然と観客にも伝わるように演出されています。例えば、保険のチラシ。あるいはタクシーで流れるラジオや、LGBTQのパレードを伝えるニュース。テレビ、ラジオ、広告、それら一つ一つのリアリティが圧倒的に高いのです。
妊娠しながらも働く隣の店舗の店員・那須沙保里との会話を含め、そうした様々なディテールは全て、恋愛、結婚、出産、子育て、という性愛を中心とした価値観に集約していきます。先述した細かい演出にも、その価値観が透けて見えるからこそ、観ていてキリキリと胃が痛みました。
さらには、自分たちとは異なる価値観の人間が存在することを考えていない無神経さ。彼氏・彼女の有無を聞くなど、他人ののプライベートに土足で踏み入る無遠慮さ。田舎の人間ならではの様々な「狭さ」が、社会の窮屈さを増幅させていました。
招待された披露宴で、夏月は同級生の佐々木佳道と再会。中学時代に互いに秘密を共有した二人は、以降ずっと自身の性癖を押し殺してきた。社会に対して窮屈さを抱く彼らの表情は、無感情もしくは愛想笑い。自分らしく生きるのを、とっくの昔に諦めた諦観が滲み出ています。
夏月は中盤まで、ほとんど言葉を発しません。彼女の独白で話が進んでいく原作とは異なり、本心が読めません。しかし明らかに彼女はストレスを抱えています。周囲の無意識によってコップに溜まっていった「ストレス」という名の水。大晦日、それが遂に溢れ出てしまいます。
理不尽な理由で逆上する沙保里に対し、「うっさい」「話しかけんな」と呟き、強い目力で睨みつける夏月。帰宅すると『はじめてのおつかい』風の番組を母親に見せられ、家を出る。頼りたかった佳道の家に行くも、どうやら彼は不在のようだ。「死ね」「死んじゃえ」と呟き、車のアクセルを強く踏む。
間一髪、車の目の前を佳道が通りかかり、自殺は失敗に終わります。しかしこの一連の流れは、原作よりも八方塞がり感が増している話運びに加え、映像的に緊迫感と臨場感があり、本当にハラハラしました。
群像劇をシンプルにまとめた改変
夏月と佳道の物語に加え、今作には二つの軸が用意されています。一つは、寺井啓喜の物語。横浜在住の検事の彼には、10歳の息子・泰希がいる。不登校状態の彼は、学校に行かずとも勉強はできる、と主張する同い年のインフルエンサーに影響を受けていた。
NPO法人の活動で出会った同い年の冨吉彰良とともに、YouTube活動を始める泰希。二人は登録者数の増減や寄せられるコメントに一喜一憂していた。反対する啓喜とは対照的に、妻の由美は泰希の生き方を応援している。
啓喜は「普通」の生き方を息子に歩んでほしい。家事や子育ては専業主婦の妻に任せているが、口出しはする。妻に対して「ありがとう」を言わない。前時代的な「あるべき夫」像を具現化したような存在。徹頭徹尾、私は彼のことが嫌いでした。
啓喜役の稲垣吾郎さんに対し、監督の岸善幸さんは「『観客は稲垣さんを基準に映画を観て、やがて自分たちのことに翻って、あれ?と疑問が持てるような存在として演じていただきたい』とお伝えしました」と語っています(※2)。
※2:10/31(火)東京国際映画祭🎬岸監督QAレポート – 正欲より引用
冒頭の時点で私が彼に嫌悪感を抱いたのは、私自身が夏月や佳道の境遇に近い人間だからなのかもしれません。世間一般で楽しいとされている事が苦手な自分にとっては、劇中に映される広告に耳が痛くなりましたし、啓喜の一挙手一投足に嫌気が差しました。
とはいえ、彼の気持ちに全く共感できないわけではありませんでした。泰希が支持する不登校インフルエンサーは、実在のYouTuberを連想させます。ゆえに息子の活動を良く思わない啓喜の気持ちも分かる、というのが上手いバランスでした。
さて作品のもう一つの軸は、大学生・神戸八重子の物語。学祭実行委員の彼女は、企画した「ダイバーシティフェス」の準備に奔走している。その挙動からも明らかなように男性恐怖症の彼女は、学祭で関わったダンスサークルの諸橋大也に惹かれていく。
本作の監督を務めるのは、『前科者』(2022)などの岸善幸さん。『あゝ、荒野』二部作(2017)で監督とタッグを組んだ、港岳彦さんが脚本を執筆しています。映画化にあたり、原作にあった5人の周辺のエピソードを削ってシンプルな話になっており、一本の映画として見やすくアレンジされていました。
それだけでなく、2018〜19年という時代設定は変えていないものの、BLを題材にしたヒットドラマや、平成から令和へ元号が切り替わる空気感は排除されています。それにより2020年代っぽさすらも匂わせており、より現代の観客が入り込めるように調整されていると思いました。
「ずっとこの星に留学しているような感覚」や「大晦日とか正月とかって、人生の通知表みたいな感じがする」など、小説にあったパンチラインはそのまま活かすことで、朝井リョウ作品の雰囲気はしっかり残っていました。
映画的な「食」描写
映画オリジナルの描写に関しても素晴らしかった。水が溢れ出たコップを映したファーストカットや、タイトルが出る夏月の部屋でのシークエンス。どちらも作品のモチーフである「水」を強烈に印象付ける役割を果たしていました。
大晦日の夜に再会した夏月と佳道はすぐに打ち解け、横浜で同棲を始める。それぞれの部屋で寝て、食事も別々に用意する、「普通」ではない共同生活。本編中の食事に関する描写は、ほとんど映画化にあたり持ち込まれた要素であり、そのどれもが印象に残るものでした。
佳道に関しては、職場でサンドイッチを食べていたり、自室の枕元には酒の空き缶がいくつも置いてあったり、朝食で食パンにマヨネーズをかけて食べていたり、その食事内容からは彼が全く食に興味がない様子が一目で分かります。
作品序盤、夏月が回転寿司店のカウンターに座ってえんがわを食べているとき、彼女の目は死んでいました。対照的に同棲後は、慣れない手つきで卵焼きを楽しそうに作っています。食に興味がなかった彼女が、「生きよう」という考えを持つようになったのがこの場面で表現されています。
寺井家に関しても、食事描写は見逃せません。冒頭で由美は焼き魚を食卓に並べていましたが、話が進むと、簡単に作れるオムライスやレトルトカレーに料理が変わっています。おもちゃがリビングに散らかっているのと同様に、彼女の関心の変化が、食の変化によって表現されていました。
原作には、物語の鍵となる「事件」が初めに明かされた後、時制が戻り、事件に向かって物語が進んでいくハラハラ感があります。対して映画版では、中盤で唐突に事件の存在が明かされます。佳道や夏月に感情移入していたからこそ、ショッキングに感じられました。
佳道は同じフェチを持つ人と繋がるため、「FUJIWARA SATORU」こと大也と、DMでコンタクトをとっていく。大也が連絡をとっていたもう一人の人物を含め、三人で水の様子を撮影する約束を取り付ける。しかしこれが、衝撃の展開に繋がっていきます。
彼らが公園で子供たちと遊ぶシーンで、劇中初めて出てきた男・矢田部陽平。小学校教師の彼が、児童売春の容疑で逮捕された。押収された証拠の中に、佳道と大也と撮影した映像が見つかり、二人も逮捕されてしまう。
ちなみにここでも、食べ物が巧みに演出に取り入れられていました。夏月が好きな蟹クリームコロッケ。帰宅途中に商店街で買ったコロッケがアップで映され、その後彼女が自宅に着くと、佳道が警察に連れていかれる場面を目にする。観ていて本当に辛い流れでした。
最後に用意された「対決」
検事の啓喜は、理路整然と被疑者への聴取を行っていく。たびたび挟み込まれるその振る舞いにはゾワゾワします。そんな彼が信じるのは、一般的な「当たり前」の生き方。男性として、夫として、父親として「正しく」あろうとする。そして自分の世界とは異なる世界が存在するのを知ろうとすらしないのです。
演じているのは、稲垣吾郎さん。風船を膨らまようとするも失敗する様子や、由美と泰希との二対一の喧嘩が、非常に気まずい。映画オリジナルのこれらの描写が、彼が「正しく」あり続けることの惨めさを際立たせていました。
特殊な性癖を持つ夏月を演じるのは、新垣結衣さん。キャスティングについて岸監督は、「これまで演じた役柄が、夏月とは対極のイメージを持たれている人に演じてもらいたかった」「夏月役を考えたときに真っ先に名前が浮かびました」と語ります。

その狙い通り、新垣さんの過去作のイメージを覆す演技にずっと引き込まれていました。先述した死んだ目での食事だけでなく、ちょっと猫背で歩いている姿には、夏月の自己肯定感の低さが表れていました。
啓喜と夏月が出会うシーンは、劇中で二回のみです。一回目は、街中での偶然の出会い。社会に「奥さん」と認定された夏月の喜びと、啓喜の家庭環境の変化が端的に描かれています。さらにこのエピソードが、二回目の出会いのドラマ性をより強調していました。
二人が再会するのは、映画ラスト。啓喜が夏月に聴取を行う。いわば「対決」です。「有り得ない」と結論ありきで決めつけてくる啓喜を前にし、夏月は決して口を割りません。
「顔面の肉が、重力に負けていった」と原作で書かれた、社会への諦念が表れた彼女の表情は見事でした。佳道役の磯村勇斗さんもまた、話し方や表情の節々に諦念を纏わせていて素晴らしかった。
オーディションで選ばれた他二人の演技も見逃せません。佐藤寛太さんが演じる大也は、まばたきをしないため、怖くもあり、目の奥に虚空が広がっているようでもありました。自室で静かに流した涙が、美しかったです。
東野絢香さんが演じる八重子は、映画初出演とは思えないほど実在感がありました。どちらにも理があるけれど、どちらにも否がある。すれ違い続けた大也と八重子が意見をぶつけ合う終盤、彼女の心の叫びは必見です。欲を言えば、映画化にあたり省かれた二人の対決も見てみたかったです。
脇を固める俳優陣に関しても、夏月と佳道を披露宴に誘った西山修を演じる渡辺大知さんが、彼ならではの絶妙なウザさがあって良かった。また泰希役の潤浩さんが、一人の人間としての自我があるけれど、年相応の夢を見ている等身大な雰囲気を出しており印象に残りました。
生きるために求める繋がり
学校生活の窮屈さを描いた、第22回小説すばる新人賞受賞作『桐島、部活やめるってよ』。仲間同士の潜在意識を暴いた、第148回直木賞受賞作『何者』。そうした朝井さんの過去作からも分かるように、社会を見通す解像度の高さが繊細な描写の端々から伺えます。
同二作と『正欲』の共通点として、特定のコミュニティにおいて「当たり前」「普通」「正しい」とされる価値観に振り回されたり、もがいたりする人々を描いている点が挙げられます。
中でも今作は、「多様性」という言葉の功罪を観客に突きつけています。夏月や佳道、大也といった「多様性」の外側にいる人々の存在は、私たちが生きている社会がどういった価値観を中心にして回っているのか、を浮き彫りにしました。
近年声高に叫ばれるようになった言葉ですが、ここでの「多様」はあくまでマイノリティの中のマジョリティを指しているに過ぎません。マジョリティ側の人間によって、正常と異常の線引きがされているのです。
人間が生命を維持するために必要な「三大欲求」と呼ばれる食欲、睡眠欲、性欲。誰しもが持っている欲求として多数派に認められた性欲、それがセックスです。性行為は多くの人がすることだから変態的ではなし、対して少数派の性的嗜好は「特殊性癖」と認識されています。
この社会は、生きにくい。それでも登場人物はみな、生きるために「繋がり」を欲しています。誰とも繋がりがない人生は、寂しい。分かり合える人が一人でもそばにいると、安心する。三つの軸が交差していくストーリーは、そういったメッセージを伝えているように感じました。
映画ラスト、夏月は佳道に伝えたかった言葉を口にする。聴取が終わり、宇野祥平さん演じる越川事務官とともに部屋を出る彼女。彼女の言葉を耳にして呆然とし、部屋に残ったままの啓喜を映して本編は終わります。この幕引きは、原作よりも切れ味が鋭く、打ちのめされました。
最初から最後まで、一つ一つのカットに意味が込められている本作からは、複雑なテーマに真摯に向き合った製作陣の姿勢が伝わってきました。原作のメッセージを的確に汲み取り、映画的にアレンジして伝えている傑作だと思います。
最後に
家庭環境、性的指向、容姿。あらゆる背景の人に観ていただきたいですが、特に孤独や寂しさに苦しんでいる人に薦めたい作品です。きっと優しく背中を押してくれるでしょう。私自身も、鑑賞後に心が軽くなりました。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
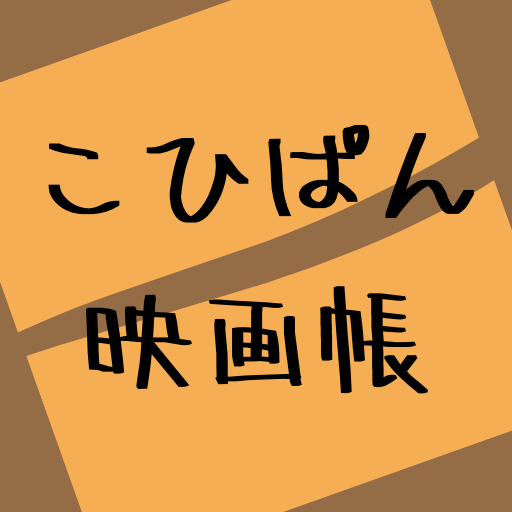
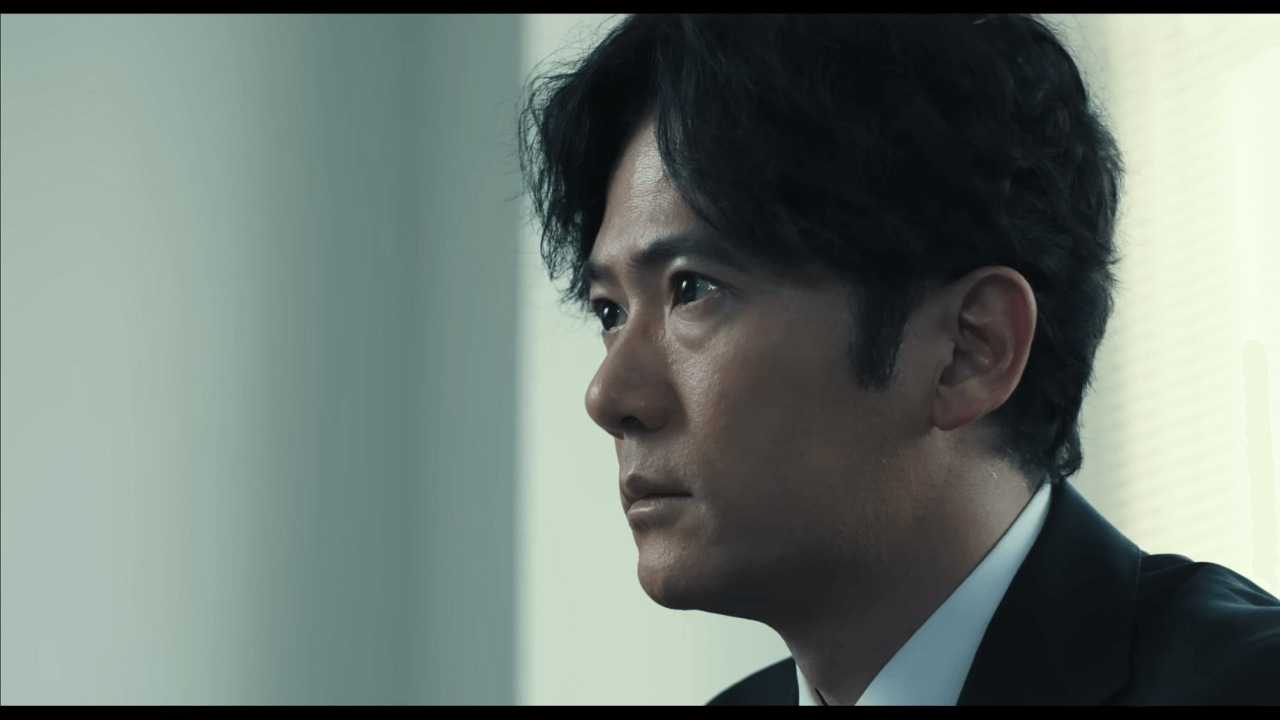


Comments